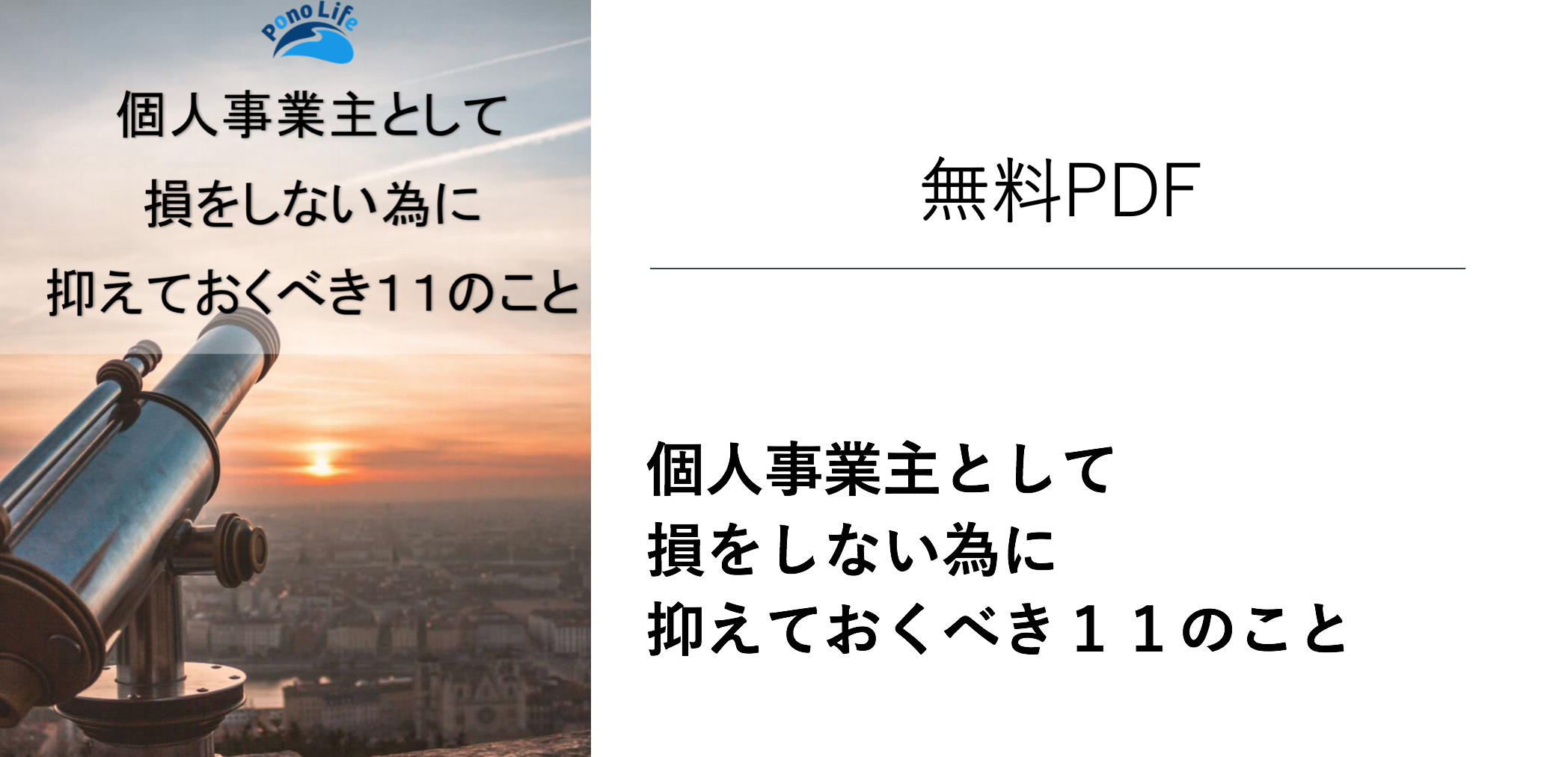目次
個人事業主が発信をすることって大切ですか?
そう聞かれたら迷うことなく「はい」と答えます。
特に個人事業主として働いてるのであれば、自分の存在を知ってもらうことも必須条件です。あなたという人間を知らずにあなたの扱っているサービスを購入するということなどありえないから。
だからぼくは発信を続けます。
そうすることで、どこかの誰かの役に立つこともできるし、自分の存在を認知してもらえるからです。
自分の存在を認知してもらえるからこそ、対面でのサービスにおいてその人が抱えている問題をより高い確率で解決するお手伝いができるから。
発信をするネタ探し
どうしてそれだけ多くのことを発信できるのですか?
そう聞かれることも少なくありません。
ネタを探している、と言う認識はなく日常の中に染み付いているといったほうが正しい感覚です。
ただ言えるのははじめから出来るようになっていたわけではなく、発信すると決めているから多くのネタを見つけ出すことができているのは間違いありません。
もともと文章書くのは好きなほうなのですが、最初の頃は全くと言っていいほど文章が書けませんでした。何を書いていいのかわからなかったからです。
しかしこれも半ば無理やりですがトピックを見つけて一行でも二行でも書き続けようとすることで些細なことが目に留まるようになります。自分の解像度が変わるのです。
オフィスKukuna Bodyのブログで365日、毎日何かを書くと決めて行っていたときのことでした。
最初の50日ほどはなかなか厳しい作業でしたが、それ以降は書きたいことがたくさん溢れてきて、1日1エントリーではもったいないと思ってしまうほどでした。
解像度が変わってくることでより多くの情報を詳細にキャッチすることが出来ます。そして、自分が日常生活が感じている疑問を文章化していくという作業を繰り返します。
日常で感じている些細な疑問ですが、これは記憶に頼ろうとすると忘れてしまうので思いついた時にすぐにメモをとるようにしています。
手書きのメモ帳でもよいでしょうし、携帯アプリのEvernoteやGoogle keep などを好んで使っています。ツイッターやFacebookを使っている方はそちらに書き込んでみてもよいでしょう。
なんにせよ記憶に頼るのではなく記録をするということで、ネタ探しというのはぐっとやりやすくなります。
発信する媒体と目的
発信する媒体についてはどれがいいのか聞かれることがあります。
結論から言うと何を目的に利用しているかということになりますが、まずは自分が使いやすいものと自分の対象とする人たちがどの媒体を主に使っているかというところがポイントになるでしょう。
これについては今後別のエントリーで記載していこうと思います。
僕自身はこのブログ、オフィスのブログ、Facebook、ツイッター、note(無料記事、有料マガジン、月額課金制マガジン)、そしてメルマガ、またメルマガの中で配布する無料のPDF、(あとInstagramはほぼ遊び)を使っています。
その中で少なくとも2つか3つの媒体において、毎日発信をしています。
それぞれにおいて目的は異なります。
何を目的としているかについてもまた別のエントリーで一緒に説明をしたいと思います。
ただこれだけ発信の様々な媒体でするようになると気付くことがあります。
それは確実に届く層が違うということ。
例えば最も広く周知されて利用されている媒体はFacebookであることに異論ないと思います。
しかしながら当初はよくあるとされていた実名性や本人とのつながりがなければ交流できないというシステムは、いわば親戚との集まりのようなイメージ。
ですから何かしら自分と関わりの強い人たちの世界。
これには良い面も悪い面もあり、良い面では安心感がありますが悪い面ではその世界に染まってしまったり、新しい世界に1歩踏み出すことができなかったりするということです。
個人事業主として発信することに選んでいる媒体はTwitterとnote
最近ボクがとても楽しく使っているのはツイッターとnoteです。
これらはしばらく使っていない時期もあったのですが、より発信を心がけるようになることで自分よりも多くの人たちに言葉を届けられている人たちはどのようなことを意図して発信をしているのかとても気になるようになりました。
それであればその人たちが使っている媒体で、その人たちから学べばよいという考え方です。
自分の言葉で多くのことを伝え、数千人やなんまん人もの人に影響を与えているいわゆるインフルエンサーと言われる人たちは本当によく研究をし勉強し発信を積み重ねています。
そういった方々は僕が所属しているような健康産業であったり、フィットネストレーナー産業の方ではありません。
自分という商品を全面的に押し出して活動をし、表現をしながら生きている人たちです。
その熱量はハンパないです。
だからこそ人の心を動かしたり、影響与えることができるのだと思います。
個人事業主として発信を継続することのメリット
発信することを意識して積み重ねてきた中で周りがどういうことにより悩んでいるのか、どういったものを求めているのかということにアンテナがはられるようになりました。
より明確に自分の周りにいる人達の悩みに答えることができるようになりました。
noteで有料記事を発行することで気づいたこと
そして、特に最近はnoteで有料の記事を発行しているなかで、気付くこともたくさんあります。
どういった形で提供していくことでより多くの人に読んでもらえるかを真剣に考えます。
無料のものは多く読まれても有料のものになった途端に読まれないということがよくあるからです。実際、影響力が高いと思われている人でも100円の有料記事ですら全く売れないということがよくあります。
これは自分にとってもひとつのチャレンジでした。
記載している内容などは非常に価値のあるものだと信じています、なにせ起業から今までの失敗談をふんだんに盛り込み、その時々に今だったらどういうことを行ってその失敗を回避するかという、内容を書き連ねているのですから。
このnoteは発売して1週間ほどで50部以上が販売されました!(ありがとうございます!)
現在も好評発売中!
これを購読するためにノートに登録してくださっている方も多く、初めてのことはなんでもハードルが高いとおもうのですが、そういった障壁を乗り越えてまで購入してくださっていることを本当に嬉しく思います。
また自分自身が有料で販売する形をとるなかで、すでに表現をすることで生活をしていらっしゃる方々の有料媒体もより積極的に購入するようになりました。
お金をいただくことでより学びに投資をし、さらに多くのことを既存の読者の方たちに還元できるようにそのサイクルをより大きなものにできるように。
いままでもそういった勉強に対する投資は多くしてきていましたが、その意図がより明確になりました。
同時に少し前まではできるだけ多くの人に読んでもらいたいと思っていましたが、今は読みたいと思う人にだけ読んでもらえればいいと感じています。
これは今まで書き続けてきていたからこそ、本当に自分のことを必要としてくれる人たちが求めるものを提供していきたいという気持ちからです。
自分のことを必要としてくれる人が求めているものをより精度高く提供していけるようになる。
その繰り返しです。この思いもこれだけの数を毎日発信しているからようやくわかってきたことです。
発信は毎日続けたほうがいいの?
冒頭の問いに戻りますが発信をした方がいいのですか?
間違いなく、はいと答えます。
言葉にするという事は自分を表現すること。
言葉にできないということは、世の中に対して自分の行っていることを伝える術を持っていないということになります。
これは技術です。そして事業主として活動していく上で、磨いておくべきスキルというふうに認識しておくべきでしょう。
まだまだ僕の声も多くの人に届いているとは言い難いです。
それでも開業当初とは比べ物にならないくらいの人たちに届いています。そして感謝されています。
僕が発信する理由は1人でも多くの人の役に立ちたいからです。
自分がしてきた失敗は誰も繰り返す必要がないですし、自分がやってうまくできたことが多くの人に繰り返してほしいと思うからです。
そうすることで本来やるべきことに皆集中できるようになり、より多くの価値をこの社会に提供できると思うから。
こういった思いも発信を繰り返してきたことによって明確に文章化することができるようになりました。
ぼくは言葉を扱うことによってじゅんを表現することができるようになってきたのかなと思っています。
もっともっと表現していきたいです。
もっと多くのことを伝えていきたい。
もっと多くの人に届けたい。
もっとこの人に読みたいと思ってもらえるような発信をこれからも続けて行こうと思います。
noteの主な有料記事はこちらの3種類


こちらは月額マガジン。自分軸で生き、仕事をしていくために大切にしている考え方などをシェアしています。ブログに書いたことを膨らませたり、深掘りすることもあれば、こちらだけに書いているものもあります。
|森部高史(べぇさん)|note-2018-04-03-15-57-18-300x186.png)
noteの有料マガジン[自分軸の人生と仕事の作り方(月刊べぇ)]はこちらから!
[aside type=”normal”]初月無料、月1000円です。(注)月額マガジン「自分軸の人生と仕事の作り方(月刊べぇ)」は購読月以降に公開された記事をまとめて読むことが出来ます。先月以前に出された過去記事は単品でご購入頂くことになりますので早めの購読がお得です。[/aside]
P.S:最近「音声入力」の手軽さにも驚いていて、これにより更に発信の量が増えるようになりました。今の時代、こういったテクノロジーを使うか使わないかで、大きな差が生まれると感じています。
それではまた
森部高史